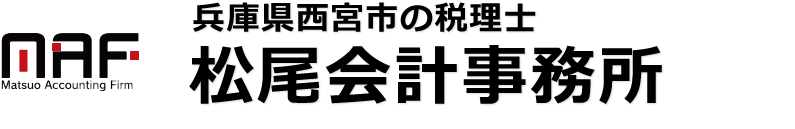論文┃第4章 産業廃棄物に係る法定外目的税の実態について⑤
第5節 産業廃棄物税に係る制度設計上の論点
1.課税タイプの選択
産廃税を設計するに当たり、図6で分類した課税タイプのうち、どのタイプを採択するかが主要な論点となる。
排出事業者を納税義務者として申告納付させる方法は、環境分野におけるPPP(汚染者負担)の原則の考え方との間に一貫性を確保できる。また、排出事業者に直接課税を行うことにより、課税負担を認識させることができ、ひいては、産業廃棄物の排出量削減努力を引き出すことが期待されると考えられる。
また、中間処理が産業廃棄物を減量する効果を有していることから、中間処理施設への搬入に対しては、一定の処理係数を適用することで、税負担を減額させる効果がある。
しかし、すべての排出事業者を納税義務者とすることは、地方団体が課税主体となることを考慮すれば、県際排出に係る課税権の帰属その他納税義務者の捕捉に係る課税技術上の問題を考慮すると、免税点を設けざるを得ないこととなる。実際、当該方法を採択している三重県においては、年間排出量1,000t未満の場合を免税点として設定しており、滋賀県にあっても年間排出量500t未満の場合を免税点として設定している。
この補足の容易性の観点から、免税点を設定することは、一部の多量排出事業者のみが納税義務者となることとなり、課税の公平性に照らして妥当し得ないものであると思われる。
次に、県際排出について検討する。例えば、区域内に事務所または事業所(以下「事務所等」という)のない企業が排出した産業廃棄物を当該区域内に持ち込んだ場合、これを課税対象とするとすれば、当然に、当該区域外の地方団体の課税権も尊重しなければならないことから、逆に、区域内に事務所等を設ける企業が産業廃棄物を当該区域外へ持ち出す場合には、これを課税対象外とせざるを得なくなる。しかしながら、排出段階で課税するに当たって、できる限り公平を確保しようとするならば、当該区域内におけるすべての多量排出業者を課税対象とすることが望ましく、この点において、整合性が貫徹できないこととなる。
他方、中間処理業者並びに排出事業者を納税義務者とし、最終処分業者を特別徴収義務者とする方法、および最終処分業者を納税義務者とする方法は、比較的少数の最終処分業者を把握することに税務執行面でのメリットが存することから、徴税コストが小さく抑えられる。これら2つの方法は、共に最終処分に着目する課税であるが、前者については、あくまでも排出事業者が税の最終負担者であることを想定しており、その意味において、排出課税と近い立場にある。そして、最終処分業者が負担した税額は、転嫁されることによって排出事業者の最終的な負担となることが期待されている。すなわち、このスキームによれば、最終処分業者を特別徴収義務者とするため、把握すべき事業者数が排出課税に比し、格段に少なくすむ。これは、徴税コストを小さく押さえられると共に、免税点を設定する必要性がなく、税負担の転嫁が完全に行われると仮定するならば、域内の最終処分場に搬入される産業廃棄物のすべての排出事業者に対して課税が及ぶこととなり、課税の公平性に準拠した方法となる。さらに、中間処理に対して課税しないことから処理係数を設定する等の手数が省かれ、結果的に、簡素なしくみとなる。その他、当該方法をすべての地方団体が採択するとなると、地方団体間の二重課税の問題は排除されることとなる。
一方、後者については、税負担は納税義務者たる最終処分業者に帰着することが想定され、排出事業者に対する産業廃棄物の発生抑制のインセンティブ効果を与えることは重視されていない。すなわち、このスキームによれば、課税のしくみが最も簡素であり、先の前者による方法におけるメリットと同様のメリットを有することとされるが、税の転嫁に関しては、最も困難な方法であろうと考えられる。したがって、結局、単なる最終処分料金の値上げとして捉えられる可能性も考えられる。
では、それぞれの県市において、産廃税の創設に当たっての課税タイプの選択の趣旨は以下の通り考えられる。三重県では、県内の管理型最終処分場の残余年数が残り少ないこと、また、近隣の県をはじめ他県からの産業廃棄物が流入過多(平成10年度45万トン)の状況にあること等の事情があり、公共関与型の産業廃棄物処分場の整備に取り組んでおり、従来から排出者責任の原則を強調していることから、関係者の理解を比較的得やすい状況にあったことが考えられる。
中国3県においては、それぞれ最終処分場の逼迫を背景としており、排出者責任の原則を基本としながらも、流入過多と流出過多の県が隣接していることを考慮して、広域体制の下で二重課税を排除できる当該スキームを採用したと思われる。
北九州市においては、他地域から大量に産業廃棄物を受け入れ最終処分をしており、市にとって、産廃税は産業廃棄物の発生抑制を促す政策手段ではなく、エコタウン事業や産業廃棄物処理施設整備を推進するための財源調達手段であると捉えられている。したがって、排出課税に固執する必要性はなく、また、市における処分料金は、他地域に比し安価であるという事実から、産業廃棄物が他地域に流出する懸念はないとの考えを基に、最終処分業者を納税義務者とする当該スキームが採用されたと思われる。
2.徴収方法の相違
次に、上述の課税タイプと密接な関係にある徴収方法について、申告納付の方法を採用するか、特別徴収の方法を採用するかが問題となる。
ここに、申告納付方式によれば、排出事業者が自ら課税標準額である排出量および税額を算定し、その算定した税額を納付することから、環境負荷に与える影響を税額という尺度で自覚することとなる。そのため、排出量削減等のインセンティブ効果が大きくなると考えられる。しかし、排出段階での申告であるため、その排出した産業廃棄物が中間処理の段階でどの程度減量化されようと、あるいは全く減量化されなかったとしても、納税額には影響を及ぼさないため、中間処理業者に対しては、減量化やリサイクルへのインセンティブ効果が希薄となると考えられる。また、莫大な数の事業者数を把握する必要性があることから、徴税コストが大きくなり、逆に、税務執行面を配慮して免税点を設定すると、課税の公平性に問題が生ずるという矛盾が生じる。その他、課税管轄権の問題も内包されることなる。
一方、特別徴収の方法は、既述のように、把握すべき事業者数が比較的少数となることから、徴税コストが小さく抑えられることとなり、また、最終処分場へ搬入されるすべての産業廃棄物が課税対象となるため、多量排出者も少量排出者も公平に税負担を強いられることになる。さらに、最終処分場への持込みの時に課税標準が算定されるため、中間処理における減量化、あるいはリサイクルへのインセンティブ効果が期待できることとなる。しかし、課税の転嫁や税負担の認識等の観点から、制度が不透明になるという欠点も有している。
三重県産業廃棄物処理税では、その第11条で「産業廃棄物税の徴収については、申告納付の方法による」と規定しており、県内はもとより、県外の排出事業者に対しても申告納付を義務付けている。これは、地方団体の課税管轄権・条例の管轄権の問題をもたらすであろう方式の内容になりつつある との識見もある。域外に排出者がいる以上、必ず域内に産業廃棄物を受け取り処理する者がいるはずであり、そのような場合には、課税の通念からいえば、域内の者に対して課税を行うほうが妥当であると考えられる。それにもかかわらず、納税事務負担や税務執行面の手数を要する申告義務を、域外の者に対して適用することに、その根拠が明確とされていない。
第3章で述べたとおり、租税制度を用いて環境税を課するのであれば、租税法の原則に従うべき であって、汚染者負担の原則は環境分野における原則であり、租税法においては、そのような原則は存在しない。もっとも、汚染者負担の原則を強調するのであれば、各排出地において課税すればよいこととなる。
3.税収の使途について
各県において創設されている産廃税については、法定外目的税として導入されており、その税収の使途に関しては、制定地それぞれの地域的特性が現れている。目的税は、前述したように、ある財政需要があり、しかも住民間に受益の程度に格差がある場合に、画一的な普通税で課税すれば公平が損なわれる場合に、受益の程度に応じて課税する例外的な租税である。したがって、そこには受益と負担に密接な関連性が存在する。地方団体としても、使途の制限された目的税は、財政の伸縮性の制約となり、税収が伸びれば浪費につながり、縮小すれば予定していたサービスの低下や廃止をもたらすこととなる。もちろん、地方税法上は使途が特定されていれば目的税として条例を制定することは可能であるが、受益と負担に密接な関連性のない租税を目的税とする必要はない。
そこで、目的税として制定する場合、どのような使途に用いるかが論点となる。各事例を元に概観した産廃税では、「産業廃棄物の発生抑制、減量・リサイクルのための費用」を中心に使途が特定されている。このほか、鳥取県においては、「産業廃棄物処理施設設置促進」、北九州市においては、「資源循環型産業を基軸とした新環境産業の創造」を使途として明記している点が、特徴としてうかがえる。
また、第二の論点として、税収を不法投棄の原状回復に係る費用に充当するかどうかが問題となる 。各県市は、最終処分場の逼迫等を産廃税制定の背景としており、そのこととあいまって不法投棄が多発している現状である。しかし、法定外目的税の創設の経緯から鑑みると、受益と負担の関係すなわち応益負担の原則をその賦課の根拠として説明されている限り、直接の原因者でない排出事業者または最終処分業者との関係において、因果関係を見出すことはできない。ところが、現実問題として、最終処分業者が特別徴収義務者となる場合、最終処分業者の納税額の大部分を処分料金に上乗せした場合、料金値上げを嫌悪する中間処理業者の不法投棄が発生する可能性がある。また、処分業者が排出事業者に比し弱い立場にある場合には、最終処分業者が税負担を強いられることとなり、結果として不法投棄を行うケースも想定できる。
したがって、産廃税の税収の使途を不法投棄の原状回復に充当することには、理論上矛盾が生ずるが、各産廃税条例に掲げられている不法投棄の監視体制の強化に充当することついては、妥当なものであろうと考えられる。
4.租税としての産業廃棄物税
前述した産廃税の導入について、それが①当該措置の政策目的が合理的か否か、②その目的を達成するのに、当該措置が有効であるかどうか、③それによって、公平負担がどの程度害されるか 、を総合的に考慮する必要がある。
憲法第92条は、地方自治の原則を規定するが、そのいわゆる「地方自治の本旨」とは、地方自治制度の本質的なもの、換言すれば地方団体が地方住民の住民自治に基づき団体自治を通してその固有の事務を完全に果たすための機能を保有することをいうと解されている。この機能の最も重要なものは自主財政権であり、したがって地方団体の財源の根幹を占めるものは租税であることよりすれば、これを賦課徴収する課税権は自主財政権の中核をなすものということができる。
この場合、課税目的が財源調達を目的とするかの、あるいはインセンティブを目的とするかについては、既に述べたとおり、各産廃税の条文の文理解釈からは、すべて財源の調達を第一義としていることが読み取れる。また、この他、税の価格インセンティブについては排出事業者ごとにその働く水準は異なるが、現行の税率を見る限りインセンティブ効果による減量化等を主目的として制定されているとは考えにくい。然るにインセンティブについては、税収獲得という租税本来の目的に、環境負荷に係る政策目的が副次的に混入されているものと理解することができる。憲法の規定する「租税」の概念として、金子は「国家が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するために資金を調達する目的で、法律の定めに基づいて私人に課する金銭給付である 」と述べている。すなわち、租税の実質を有するかどうかは、適用法規の決定においては、ほとんど意味を持たない ということになる。
そして、地方団体が法定外税として産廃税を課税する際には、地方税法の規律に服するのであって、法定外税の創設に必要な総務大臣の同意の手続きを踏まえなければならない。特に、消極要件(地方税法第261条、671条、733条)への抵触を避け、また、同時に非課税規定(同法第262条、672条、733条の2)の制約を考慮しなければならないこととなる。ゆえに、産業廃棄物に対する課税に限っていえば、産業廃棄物の発生は、経済活動の結果であるからして、それに応じた負担を課すことが応能負担原則に違反しているとは言いがたいし、応益負担原則の観点からも妥当しえる。したがって、最終処分施設の逼迫等を背景に、周辺整備等に係る財源を確保するという政策は、それを懸案事項として抱えている地方団体にとっては合理的なものとなり、その際に課税自主権の行使として法定外税を活用することは有効な手段であると考えられる。
最後に、税源配分について検討する。地方分権化が進めば税源配分の再構築は避けられないこととなる。現行の税源配分についても、中央政府の機能および地方政府の機能を斟酌した上で決定されたものであると考えられる。
県際排出に係る問題について、産業廃棄物が同一の域内で発生と処理が行われる場合には、問題とはならない。しかし、排出の地方団体と処理の地方団体がそれぞれ異なる場合には、課税管轄権や二重課税の問題が生じることとなる。従来から汚染者負担の原則を根拠に汚染者段階での課税を正当化してきた。しかし、複数の地方団体間にまたがる県際排出、処理について、この汚染者負担の原則を安易に適用することは租税としての妥当性を欠くこととなる。三重県における排出者課税については、日本で最初に導入されたために、この課税管轄権については条文上考慮されていないと読み取れる。当該方法を採択する後発の滋賀県においては、三重県と隣接するのみでなく、最終処分課税を採択した奈良県とも隣接していることから、これらの事項について一定の定めを設けている。
滋賀県産業廃棄物税条例第5条には、税収の帰属に関して、その第1項3号で「産業廃棄物が県内中間処理施設へ搬入された後において、当該産業廃棄物が産業廃棄物の最終処分場への搬入に対して課税地方公共団体の区域内に所在する最終処分場へ搬入された場合における当該県内中間処理施設への搬入については、課税を免除する」と規定し、また、第4号は「産業廃棄物の中間処理施設への搬入に対して地方税を課する県外の地方公共団体として規則で定めるものの区域内に所在する中間処理施設において処分された産業廃棄物が県内中間処理施設に搬入された後において、課税地方公共団体以外の県外の地方公共団体の区域に所在する最終処分場に搬入された場合における当該県内中間処理施設への搬入については、課税を免除する」と規定しており、徴収時点に関しては、「税収が帰属する県の最初の搬入で税を徴収する方式とする」こととされている。つまり、滋賀県以外の産廃税導入県の最終処分場に搬入された場合は、当該最終処分場の所在する産廃税導入県の課税権を優先し、滋賀県では課税免除となる。また、産廃税未導入の県に搬入された場合で、三重県に所在する中間処理施設に先に搬入された場合は、三重県の課税権を優先し、滋賀県では課税免除となる。要約すると、滋賀県に税収が帰属するのは、最終処分地が滋賀県である場合と、最終処分地が産廃税未導入県で、かつ、滋賀県が産業廃棄物の発生源の県となる場合の2通りに限られることとなる。
確かに、域外からの「入超」団体は、区域内・外を問わずすべての排出行為に対して課税し、より多くの税収を獲得しようとする意図は理解できなくはない。しかし、二重課税排除のための一定の定めを要すること、その他計算構造上の観点から捉えた場合、特定の地方団体が新税を導入することは、当該税収が法人税法上損金として、もしくは所得税法上必要経費としてそれぞれ算入されるものである場合には、他の地方団体または国の税収を侵食させる結果となることを考慮すると、「地方分権」という観点から、自主性・自立性の考え方には拮抗するが、周辺団体との協調は不可欠であると考える。したがって、結局のところ、免税点の設定により最終処分課税とその実態が変わるものでなくなる排出課税を選択するよりは、最終処分課税を採択するほうが産廃税としてはより適当なものではないだろうか。
※53 中里・前掲注44,30-39頁.
※54 青森県では、当初、産廃税の税収を不法投棄の原状回復に係る費用に充当することを検討されていたが、議会の議決を経ることはできず、不法投棄の監視の強化に用いられることとなった。
※55 大牟田電気税訴訟における非課税措置が、憲法第14条に違反するかどうかの判断基準に用いられたものを引用 『判例時報』966号,4頁.
※56 金子宏『租税法(第9版)』弘文堂,2003年,9頁.
※57 金子・前掲注53,11頁.