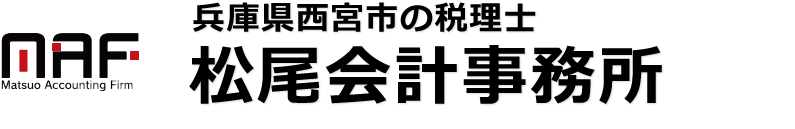論文┃第3章 法定外税の動向①
第1節 法定外普通税総論
1.沿革
現在の法定外普通税に相当する制度は、明治13年以来存在しており、「雑種税」、「独立税」の一種として内務大臣および大蔵大臣の許可を得て、法定税目以外の税として、府県・市町村ともに課することができるとされていた 。
その後、昭和25年のシャウプ勧告では、船舶税・電話税・船取得税・金庫税等の廃止を勧告し、法定外独立税は将来において減少の方向に向かうように、地方税の道府県・市町村間の税目の整理と全国的・統一的な基準による地方税財源の確立を図るべきとの趣旨から、地方税法の改正が実施され、当該改正地方税法により法定外普通税に関しての許認可制度が確立された。具体の内容としては、積極要件として、「地方財政委員会は許可の申請を受けたとき、当該申請に関わる地方団体の法定外の普通税について、当該地方団体にその税収を確保できる財源があること及びその税収を必要とする当該地方団体の財政需要があることが明らかであるときは、これを許可しなければならない」と規定し、逆に、消極要件として、「国又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となる場合、そして、国の経済施策に照らして適当でない場合、以外の場合においては許可をしなければならないと」いう要件を規定した。この消極要件については、現行の法定外普通税および法定外目的税におけるそれに引き継がれたものである。
当時の新税ブームについては、その背景として戦後復興および財政危機という切実な財政状況があり、財源確保のため課税できるものにはなり振りかまわず課税するというスタンスがあった。そのため、主に贅沢品を中心に扇風機税・ミシン税・楽器税・犬税等、実に特異な法定外普通税が存在していた。このように、戦後の課税自主権に基づく新税は、税の原始的機能といえる財源確保を最大の目的として設定されていたとみることができる。
2.課税の動向
ところが、高度経済成長とともに社会が高度化してくると、この課税自主権に基づく法定外新税の性格も変わってくる。それまでの第一義的な財源確保という目的に、地域内における負担調整という要素が組み込まれてくる。つまり、「原因者負担原則」の適用である。その背景には、それまで課税対象であった贅沢品等が一般化することで、特別に課税する理由がなくなってきたことや、住民意識の高まりにより、不合理な課税ができなくなってきたこと等が考えられる。
このような沿革を受け、法定外普通税は、1954~55年度の時点では34種類存在し、あわせて3,483の都道府県と市町村において課税されていたが、地方団体の税収総額に占める割合が低いことや、課税の公平性、徴税コストの高さ、課税客体の把握の困難さなどの理由から、後にその多くが廃止された(図5参照) 。
その後、1970年代半ばごろには、自然公園利用税、入島税、空き缶回収税、環境保全税、駐車場税、ゴルフ会員権税等の構想もあったが、最近では、湖・河川などに係留ないし停泊しているボートやヨット等への課税、場外馬券場・パチンコ店・風俗店への課税などが議論になっている。
そこで、現在制定されている法定外普通税についてまとめたものが、表1・2の通りである。県税として「核燃料税」など5種類・15団体、市町村税として、「砂利採取税等」、「別荘等所有税」、「歴史と文化の環境税」の3種類・5団体が存在しているに過ぎない。
これらのうち、地方分権一括法施行以後に制定された新たな税目としては、県税として神奈川県「臨時特例企業税」、市町村税として福岡県太宰府市「歴史と文化の環境税」の2税を挙げることができる。前者については、法人事業税の外形標準課税が制定されるまでの時限立法として制定されたものであり、平成15年度末をもって、当該条例の効力は失効することとなる。他方、後者については、観光客を対象とした、一種の駐車場税であり、特別徴収の方法によることから(有料駐車場の事業者を特別徴収義務者とする)、事業者の理解を得られず、未だ課税するには至っていない。
※37 朝日新聞・朝刊2000年2月26日付