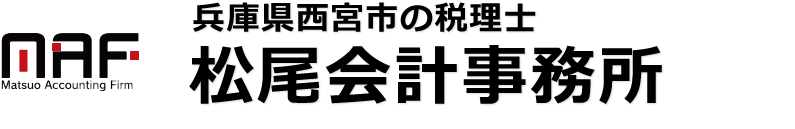役員退職金の損金算入時期について:その①
節税対策の一つとして役員退職金を支給する方法については、以前、「節税対策について」の項でご紹介しました。
損金となるか否かは、退職金の支給という「名目」ではなく、勤務実態や会社への影響力等の「実質」について判断されるということもご確認いただきました。
>>節税を目的とした「役員退職金の支給」は、こちらをご覧ください。
今回は、損金算入を行う時期について見ていきます。
損金に算入することができる役員退職金とは?
法人が役員に対して支給する退職金で、損金に算入することが出来るものは、「適正額」であることが大前提となります。
特に同族会社の場合は、株主=役員、というケースが殆どであります。
つまり、同じ人間が「株主の立場」で算定した退職金を「役員の立場」のご自身が受け取る、ということになります。
そこで、法人税では役員退職金の限度額として、次の算式を設けています。
【最終月額報酬 × 在任年数 × 功績倍率】
ここで、最終月額報酬と在任年数については、動かしようのない事実であり、恣意性の介入する余地は少ないでしょう。
ちなみに、役員報酬は、定期同額給与(毎月同じ金額を定められた日に支給)となりますので、退任の直前の月の役員報酬を高く設定する、ということは不可能になります。
また、当期末における役員の退職を見込んで、期首に定期同額給与である役員報酬を高めに改定したとしても、他の役員とのバランス、業績とのバランスを鑑みて明らかに不自然な場合には、定期同額給与とは別の法人税の規定が発動し、損金とは認められなくなります。
一方、功績倍率につては、ある程度の恣意性が介入してしまいます。
創業社長であることを理由に、倍率を2倍~3倍に設定するケースが多いですが、その根拠を示すことができるように準備しておく必要があります。
判例や判決、裁決がオープンになっていますので、倍率の設定は慎重に行わなければなりません。
税務署が役員退職金を否認する際のポイントとなるのは、そもそも論としての退職の事実と、この功績倍率、そして次に記す損金算入時期に絞られてきます。
役員退職金はいつの時点で損金に算入するのか?
法人が役員に対して支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。
この場合の損金算入時期は、次の通りとなります。
原則
株主総会の決議等によって、退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度
特例
法人が退職金を実際に支給した事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度
2つの留意点
1.退職金が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、その時点では損金の額に算入することはできません。
※つまり、「内定額」ではなく「確定額」でなければなりません。
2.法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となります。
※つまり、支給する事業年度の損金となります。
退職時に年金の総額を未払金として損金経理した場合においても、その全額が損金の額に算入されるわけではありません。
したがって、原則処理では、株主総会での決議時に「債務が確定する」との判断になります。